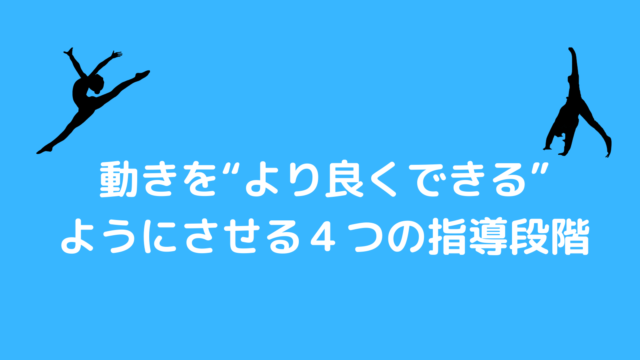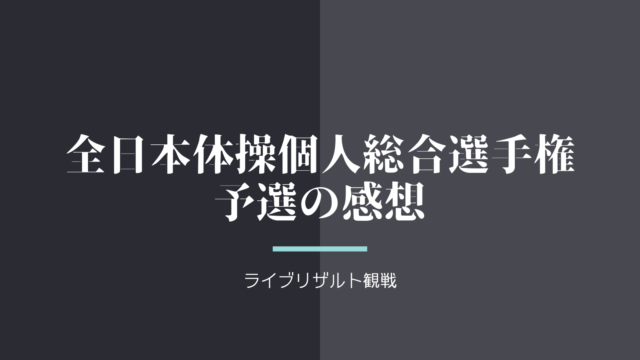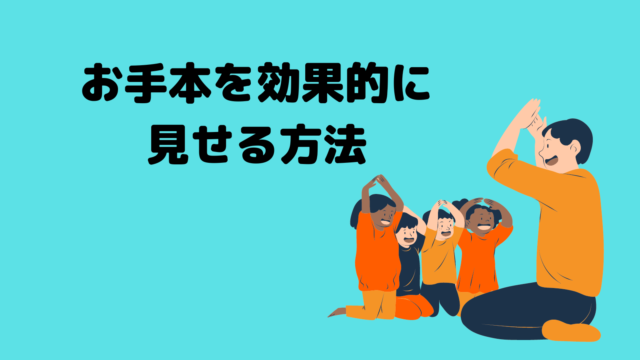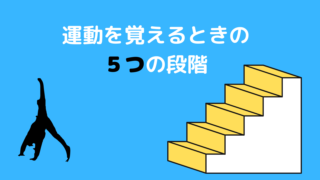【跳び箱】開脚跳びのコツ「おしりをあげる」は危険!その理由と上手に跳べるコツ

- 「開脚跳びができるようになりたい!」でも、怖い…
- 「おしりをあげて!」と言われたけれど、うまくできない…
- できない子に対して、どうアドバイスしていいか分からない…
このようなことはありませんか?
学校や幼稚園、体操教室などで、跳び箱の開脚跳びをするとき、
先生やコーチに、「もっとおしりをあげて!」というようなアドバイスをされたことはありませんか?
しかし、この「おしりをあげる」というアドバイス、正しく使わないとリズムが乱れたり、最悪頭から落ちてケガにつながる危険もあります。
では、どのようなポイントを意識して、練習するといいのでしょうか?
私は過去に幼児から大学生まで、1000人以上に器械運動を教えてきました。そんな中でも、「おしりをあげる」と上手くいかない…といった子に指導した経験もあります。
そこでこの記事では、
- 開脚跳びで「おしりをあげる」が危ない理由
- 跳び箱の開脚跳びで意識してほしいポイント
について紹介します。
この記事を読めば、跳び箱の開脚跳びのコツについて分かります。
跳び箱が跳べずに困っているという人はもちろん、跳び箱を跳べるように教えてあげたい!という人もぜひ読んでください。
開脚跳びで「おしりをあげる」が危ない理由
跳び箱の開脚跳びで、「おしりをあげる」という意識が危ない理由は主に2つあります。
- 切り返し動作がうまくできなくなること
- リズムが崩れてしまうこと
1つずつ、解説していきます
切り返し動作がうまくできなくなる
開脚跳び(パーとび)では、とび箱に手をついて、「切り返し動作」をおこなうことが必要です。
「切り返し動作」とは、上方向への勢いを、手のつきによって、前方への勢いに切り替える役割を果たす動きです。
「おしりをあげる」ことを意識すると、とび箱に手をついてからも、下半身を上げようとする動きが強く出てしまうことがあります。
下半身が上がり続けると、前方への勢いに切り替えることが難しくなります。
つまり、「おしりをあげる」という意識によって、開脚跳びにとって重要な「切り返し動作」を妨げてしまうことがあるのです。
もし、切り返し動作がないと、下半身が上がりすぎて、頭からマットに落ちる、というような危険な着地になってしまいます。
一度でもそのような危ない着地をしてしまうと、次も頭から落ちそうで怖い…という気持ちになってしまうことも少なくないので、注意が必要です。

開脚跳びのリズムが崩れてしまう
開脚跳びでは、
- 足で跳ぶ(ロイター板)⇢手で跳ぶ(台上)⇢着地
という流れで実施されます。
このとき、
- あし → て → あし
という順番で、リズムよく実施されることが重要です。
しかし、「おしりをあげる」ことを意識すると、このリズムが崩れてしまうことがあります。
おしりをあげようとすると、手をつくタイミングが、”ロイター板を踏んだあとすぐ” もしくは ”ロイター板を踏むのとほぼ同時”になってしまうことが多くあるのです。
つまり、「あし → て → あし!」のリズムになるところが、
「あし て!、、あし」というようなリズムになってしまいます。
このように、リズムが変わってしまうと、うまく跳ぶことができません。
手をつくのが早すぎると、前方へと身体を移動させることが難しくなってしまうからです。
また、手を踏切り足と同時についてしまうと、台上前転のようにおしりが高く上がってしまって、頭から着地してしまう、という危険があります。
「次も頭から落ちそうで怖い…」という気持ちになると、手を前へつくことができずに、余計にリズムが崩れる、というように悪循環に陥ってしまうこともあるのです。
開脚跳びで意識してほしいコツ
ここで、開脚跳びの重要なポイントを紹介します。
それは、「ぐっ・とん・ぱ!」というリズムです。このリズムを意識して跳ぶ、ということを普段から教えています。
「おしりをあげる」が危ない理由 で述べたように、「おしりをあげよう」と意識すると、リズムが崩れて、頭から着地してしまう危険性があります。
そこで、
- ぐっ = 足でロイター板を踏むとき
- とん = 手をとび箱につくとき
- ぱ! = (開脚後)足が地面につくとき
というように、「ぐっ・とん・ぱ!」のリズムを意識することで、自然と「あし、て、あし」の順でリズムよく実施できるようになっていきます。
とくに、はじめの「あし、て」のところが同時にならないように、「ぐっ…とん・ぱ!」というように意識することが重要です。
”足でロイター板を踏むとき”と”手をとび箱につくとき”が同時にならないようなリズムになればよいので、
「ぐっ・とん・ぱ!」だけでなく
- とん・とん・とん!
- タン・タン・タン!
- いち・に・さん!
といった言い回しでも構いません。子どもや生徒のなじみやすい言葉で、リズムをとってみてください。
開脚跳びのコツを習得するための練習法
切り返し動作から練習する
まずは切り返し動作の練習から始めましょう。
とび箱1段(またいで足がつく高さ)を2.3台置いて、
手 → 足 → 手 → 足 と交互について進んでいく練習をしましょう。
このとき、
とん → ぱ! → とん → ぱ! とリズムをつけていきます。
慣れてきたら、次の練習へいきます。
次はとび箱1段を1台にして、「とん、ぱ!」のリズムでとび箱に手をつき、1回でできるだけ前へ移動できるように練習をしましょう。
とび箱より前へ足がつくようになるまで、練習を重ねていきます。
(参考:三木史郎,器械運動の動感指導と運動学,明和出版,2015,p.92)
踏切の動作を足して、開脚跳びをする練習
とび箱よりも前へ足がつくようになってきたら、
ロイター板をおき、とび箱を2段(またいでぎりぎり足がつかない高さ)にします。
ロイター板の上で立った状態から、1段のときと同じように「とん、ぱ!」のリズムで跳んでみましょう。
はじめは、台上に座ってしまっても構いません。
おしりがつかずに前へ着地できるまで、練習を重ねていきます。
このとき、手をつくときの「とん!」を強くしていくことがポイントです。
跳び越せるようになったら、2.3歩ほど助走をつけて、「ぐっ、とん、ぱ!」のリズムで跳んでみましょう。
このとき、「ぐっ」と「とん」が同時にならないようにすることがポイントです。
どうしても同時になってしまう場合は、より前方(遠く)に手を着くことを意識すると、うまくいくこともあります。
小さい子が練習する場合は、手をつく位置に目印をつけてもよいですね。
このとき、子どもの大きさに応じて、真ん中あたりでも構いません。
「ぐっ、とん、ぱ!」のリズムを身につけることを優先させていってください。
まとめ
跳び箱の開脚とびについて、「おしりをあげる」が危険な理由をあげ、コツと練習法について解説しました。
ここであげたコツや練習法が全員に当てはまるわけではありません。
かりに今回の方法でできなくても落ち込む必要はありません。
自分や教えている人に合う方法を見つけてみてください!
今回紹介した練習法は、実際に私が教えている内容に加えて、下記の本の内容も参考にしています。興味がある人は、ぜひ読んでみてください。
(2026/02/04 10:26:03時点 楽天市場調べ-詳細)